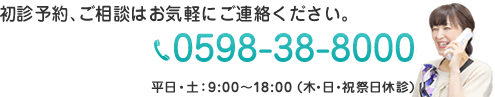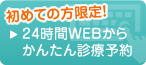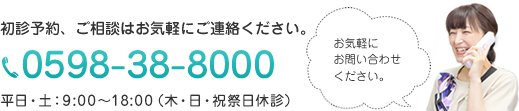せこ歯科ブログ
CiAOアライナー矯正セミナー第1回受講
今回は、Ciaoアライナー矯正のセミナーを受講しました。
Ciaoの主催をされている高津充雄先生は大阪府吹田市で開業されていて、元々はブラケット矯正治療をメインにしていたとのことでしたが、最近ではほぼすべてインビザラインによるアライナーでの矯正治療を行っています。
アライナー矯正治療とワイヤー矯正治療ではそれぞれで特性があるので、それぞれに治しやすい歯列治しにくい歯列が異なってきます。また、歯の動き方にもやはり違いがあります。
ブラケット矯正では、臼歯部はかみ合っているけれど前歯がかみ合っていない歯列、いわゆる『開咬』と言われる状態の矯正治療は難しいとされていて、臼歯部にミニスクリューのインプラントを併用するなどして、移動させる歯牙に対する固定源を作らなければならず、従来のブラケット矯正治療においては難症例に当たるものでした。
しかし、インビザライン矯正治療ではアライナーは奥歯の咬合面を覆うことによりマウスピースをはめた時のようにかみ合わせが高くなります。これが開咬の状態に対する歯列改善に非常に効果的に作用し、アライナー装着時に臼歯部の咬合が強く当たる環境下の歯牙に対して歯槽骨内で歯根移動しやすいように歯牙に適正な矯正力をかけてあげることで臼歯は骨内に沈み込む移動様式である圧下が生じて、開咬の歯列が改善されていきます。
なかなか文章表現だけではイメージしにくいですが、従来法のブラッケットでは難症例とされた開咬の状態でも1年未満で改善されるのはアライナー矯正治療をしていてすごく大きなメリットを感じます。
インビザライン矯正では、最終どのような歯列になるかもクリンチェックというシミュレーション動画をみて治療計画を見ていただけるので、治療前でもイメージがわきやすいと思います。
今回のブログ内容はインビザライン矯正の特徴のほんの一部ですが、またブログで紹介していきたいと思います。
せこ歯科クリニック 福田泰久
東京にて、CSTPCセミナー3回目を受講してきました。
こんにちは。せこ歯科クリニックの渡部です。
6月22.23日でCSPTC一年間コースの第3回目を受講してきました。
今回、デジタル活用の有用性を感じた2日間でした。せこ歯科でも使用されているデジタル画像をCT画像、顔貌写真を併用することにより明確な治療ゴールができることに感銘を受けました。今までの歯科治療ではそれぞれ別々の情報でしかなかったものが画像とコンピューターで重ね合わせをすることにより、どこの部位にインプラントを入れるとよいのか?どのような位置に矯正を用いて歯を移動すべきかなど様々な情報が得られることを学びました。より精度の高い治療をめざして今後も学び続けます。
1人目の発表の先生からは、インプラントを入れるべきか?患者さんにとって知識を入れることによって本当に必要なことは何か?ということを学びました。。
2人目の発表の先生からは矯正をするとしたら外科的な矯正が必要かどうか?診断する目を持つことの重要性を学びました。
3人目の発表の先生からは治療ゴールからどのように手順を踏むべきかということを学びました。
4人目の発表の先生からは治療を行うべきタイミングについて学びました。
5人目の先生からはデジタル画像を用いた最終ゴールの設定と治療計画、考えの基礎をまなびました。
6人目の先生からはデジタル画像を構築するうえで歯科医師が見るべきポイントを学びました。
7人目の先生からは検査データと実際の状況との差を歯科医師がどう判断すべきかという視点を学びました。
8人目の先生からは、年齢から非常に難しいケースに対する対応に関して学びました。
今回、発表予定でしたが残念ながら順番が回ってきませんでした。ハイレベルな発表が続く中ドキドキした1か月を過ごすことになりそうです。
ディレクターの先生にはそれぞれのケースにおける改善点を細かく教えていただき、また、30年超える長期経過も見せていただきかなりの情報量に圧倒されています。一つ一つ整理してせこ歯科に役立てていきます。
愛知インプラントインスティチュート第3回目
歯科医師の前田です。
6月22日23日と講習会に参加してきました。
今回は第3回目で、インプラントから少し離れて歯周外科手術の実習を2日間ぎっしりと勉強してきました。と言っても2日間では到底足りない程の豊富な内容で、休み時間も程々にたっぷりと講習を受けてきました。
2日間を通して豚顎を用いた実習を行いました。
まずは基本的な歯肉の切開、縫合から。歯肉の切開1つの手技においても、用いるメスの種類や器具の選択、どの位置、どのくらいの深度に切開を加えるのか。最終的に治癒した時の歯肉の位置や状態をイメージしながら処置を進める必要があります。またそれぞれの口腔内の歯肉の厚さや幅は常に違うので、その事も十分に配慮しながら手技を進める大切さを改めて感じました。
また口腔内の手術をする上で術後の縫合は、その後の治癒を左右する非常に大切な手技になります。 ただ傷口を縫うだけではなく、各ケースでどのような縫合をするとより治りが早く予後が良いのか、様々な縫合の方法がありますので、行った外科手術や歯肉の状態を加味しながらより適切な縫合方法を組み合わせてより良い治癒に繋げていけるよう努めていかなければならないと感じました。
次の段階として歯周外科手術の実習を進めていきます。手術に関しては様々な種類、方法、コンセプトがあり、口腔内や歯周病の状態に応じて適切な処置をセレクトする必要があります。どの手術においても共通するのは、セルフメインテナンスをしやすい環境をいかにして整えていくかかと思います。普段の歯磨きがしやすいように、またセルフメインテナンスでは除去出来ない部分を如何にして無くしていくかが大切になってきます。
そしてインプラント治療においても今回勉強した歯周外科手術の概念がとても大切になってきます。骨の中にインプラント体を埋入して歯肉の上に上部構造が入る形状のであり、また天然歯に比べると歯肉の炎症が起きやすい事を考えると、インプラントをする上で歯肉のコントロールをする事は非常に大切になってきます。特にセルフメインテナンスがしやすい環境下にインプラントをしないと、結果としてインプラント周囲が炎症を起こしやすくなってしまったり、場合によってはインプラントを喪失してしまうリスクが高まってしまいます。それぞれの患者さんのインプラントの行う部位、またその部位の歯肉の状態を十分に把握して適切な処置が必要であることを改めて勉強しました。
次回はインプラントを模型も用いて埋入する実習を行う予定です。今回はサージカルガイドという、より適切な位置に正確にインプラントも埋入するための装置を用いた実習になります。来月の講習を楽しみにしつつ、今回学んだ歯周外科手術の内容を実際のインプラント治療や歯周病治療に生かして行けるよう日々努力していこうと感じております。
船越歯周病学研修会インプラントアドバンスコース 最終回受講

先週末の土日で、船越歯周病学研修会インプラントアドバンスコース最終回を受講してきました。
今回、このセミナーを受講したかった理由はこの最終回の「インプラント周囲炎」についての講義内容でした。
インプラントは天然歯よりも解剖学的な観点からも、口腔内の細菌に対する歯周組織の防御機能は低くはなってしまいます。
そのため、インプラント治療を行う前、そしてインプラント埋入しては行ってからも口腔内の細菌をなるべく減らしていけるようにケアを行っています。
なかなか細菌を減らすと言ってもイメージはしにくいものですが、常にこの細菌との闘いになります。
細菌さえ増えることが無ければ、虫歯や歯周病や今回のテーマのインプラント周囲炎も起きてはこないので、いかにこの細菌を減らしていけるかがポイントになります。
日々の自宅でのブラッシングや、クリニックで口腔ケアのサポートしていく事が基本的な大切なことになります。そしてケアがしにくい部位対してはケアがしやすいように治療や、詰め物や被せものを修繕していくことも合わせて大切なことになります。
例えばせっかく入れたインプラント周囲に汚れがたまりやすい詰め物があると、やはりその周囲は細菌が増えやすい環境であると言えます。するとそこから近接するインプラントの表面に細菌が付着しインプラント周囲炎を引き起こす可能性が増えることになります
なるべくは、インプラント周囲に限らず口腔内全体を見た時に、自身でのブラッシングで十分汚れが取ることができるセルフケアがしやすい環境を整えていく事も非常に大切なことだと思います。
歯磨きをしていて磨きにくいところがないか?
食べ物がたまりやすく、取れないところがないか?
など一度確認してみて、もしそのような所があれば一度相談してください。
今回インプラント周囲炎が起こったらどのように治療していき、減ってしまった骨をどのように再生させるかについて学びましたが、実際にその治療で行っていくことはクリニックでの治療と並行して
基本の口腔ケアを徹底していくことの大切さも感じました。
インプラントを長期で長持ちさせていくためには、インプラント体本体の選択から始まり、外科的術式、歯周組織の仕上がり、補綴の形態や方法などのポイントがあります。
今回のセミナーを受講して、長期的予後を実現させるためのインプラント歯周治療を一貫して学ぶことができたので、日々の診療に活かしていきます。
せこ歯科クリニック 福田泰久
インビザライン矯正の勉強会に行ってきました
せこ歯科クリニックの福田です
先週木曜日に東京で開催されたMAアソシエイツのインビザライン矯正のセミナーを受講してきました。
せこ歯科クリニックでは成人矯正治療の場合、ブラケット矯正で治療する場合とマウスピース矯正であるインビザライン矯正のどちらかで矯正治療を行っています。
成人矯正治療となると、やはり従来からあるワイヤーで歯を動かすブラケット矯正が患者さんには馴染みがあり、マウスピース矯正はまだすごく珍しく感じられる方も多い印象です。
しかしインビザライン矯正も日本導入されて20年以上経過し、今やブラケット矯正を主に行っていた先生もマウスピース矯正のみで治療を行っているようになってきています。せこ歯科でも開業当初よりインビザラインは行っています。
ブラケット矯正では治しにくいケースもインビザラインでは治しやすいものもあり、その効果を実感するセミナーでした