2025年11月24日
11/23、24で広島でセミナーに参加してきました。

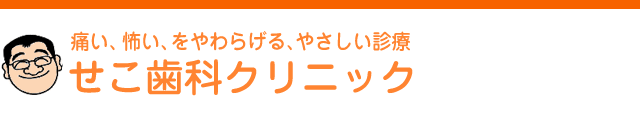

歯科医師の前田です。
前回で歯の神経をいかにして残していくか(神経を取らずに処置をするか)に関してエビデンスベースに基づいた処置の選択や材料の操作方法について学んできました。今回のセミナーでは、その後の修復処置として直接法と間接法について講義を受け実習を受けてきました。
どちらの方法において歯の中の神経をより長期に保存していくため様々な考慮をしていく必要があります。また長期の歯の保存をするためには咬合機能の回復、審美性の回復、隣の歯との隣接面の形態の回復が不可欠です。それ以外にも様々なチェック項目を総合的に判断して適切な治療方法、材料のセレクトをしていく事が大切になります。
どの方法においても、歯に別の素材を引っ付けるので、つける前の接着処理と言うのがとても大切です。処置を行うはの状態によって接着処理の方法は変わり、より適切な処理を行わないと歯の予後にも大きく影響してきます。普段の診療においても毎日のように行う処置ではありますが、より質の高い治療をしていくためにはここまでこだわる必要があるのかと驚嘆しました。様々な接着材料の使用方法や比較も論文ベースで講義してもらい、また、接着の度合いを目視、数値化、度合いを図る事が出来ないからこそ出来る限りの処置を講じる必要があるという話に感銘を受け、今後の臨床にぜひ生かして行きたいと感じました。
次に直接法(ダイレクトボンディング)の実習をマイクロスコープを用いて行いました。歯の形は人それぞれ違います。治療を行う歯に適切な形、より審美的に調和したものを時間をかけて丁寧に詰め物を行なって行きます。何度もポイントを教えてもらいながら実習を重ねていくと、徐々に理想的な形態を付与できるようになりました。より自然で機能的な形態を付与出来る様に日々努力をして行きたいです。
そして間接法(セラミック修復)についても講義を受けました。セラミックの歯の削り方は、保険内の金属とは全く異なります。誤った削り方をすると、せっかく良質な素材にもかかわらず外れてしまったり割れてしまうリスクが高まります。より丁寧な削り方、またより適切な接着処理が長期維持には必要不可欠であることを学びました。
今回も沢山の知識、技術を学ぶ事が出来ましたので、普段の診療に生かしていけるよう日々取り組んでいきたいと考えております。

こんにちは。せこ歯科クリニックの渡部です。10/4.5と北海道にて越前谷先生のインプラントのALL on X のセミナーを受講して来ました。今回はベーシックコース。ALL on X の基本を学び、ライブオペを見学させていただきました。
ライブオペでは先生はものすごい早さで、いつも使っているインプラントより長いインプラントを軽々と埋入していました。埋入時のトラブルにも軽々とクリアをしているのか、見ていると簡単にできそうな気になっていました。しかし、午後からの実習で長いインプラントを実際埋入してみて、いかにコントロールの難しい事をしていたのかを実感しました。長いインプラントを丁寧に骨の真ん中に埋入する事が難しく、ハイレベルな治療になるのか。見るのと自分が実際するのはこんなに違うんだなぁって気づけました。少しでも越前谷先生の技術に近づく為にも一つひとつの基本的な技術にこだわりを持って治療を行い続けていこうと決心しました。
越前谷先生とは去年参加した年間のセミナーでとてもよくしていただき、人間性もものすごく懐の深い先生です。今回のセミナーを通してさらに人間性の素晴らしさも実感致しました。
このようなぎ貴重な見学、セミナーに参加させていただきありがとうございました。1年後、せこ歯科で実現できるよう一回一回の治療を一日一生の思いで治療していこうとわくわくした思いを感じるセミナーでした。
貴重な体験させて頂きありがとうございました。 渡部
